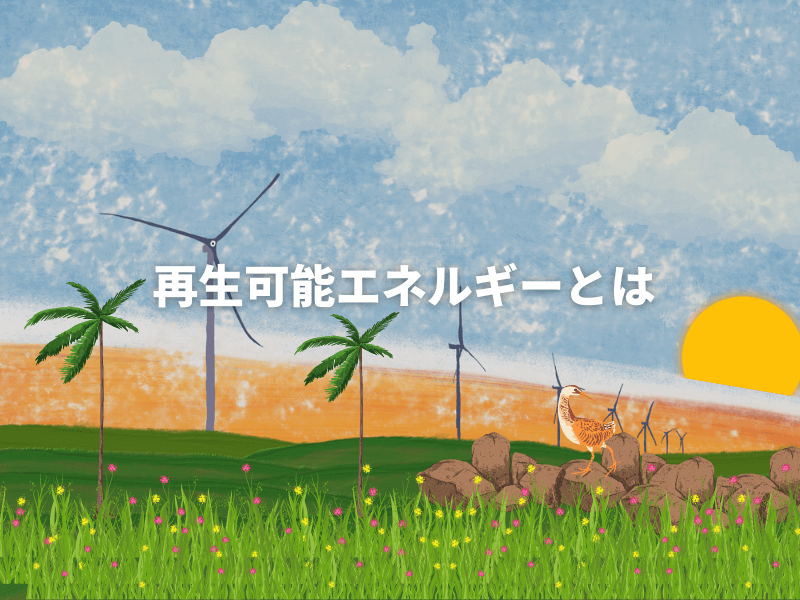
世界的な環境意識の高まりから「再生可能エネルギー」というキーワードを耳にする機会も多くなってきていると思います。しかし、「再生可能エネルギーとはなにか?」 「なぜ重要なのか?」について具体的にわかっていない方も少なくないと思います。
今回は、再生可能エネルギーの概要と重要性、および他のキーワードの違いを中心に再生可能エネルギーの全体像を掴んでいきたいと思います。
再生可能エネルギーとは?
再生可能エネルギーは枯渇性エネルギーである石油や石炭といった化石燃料と異なり、太陽光や風力、バイオマスなどの持続的に再生可能なエネルギーのことです。再生可能エネルギーはCO2を排出しないため、地球環境保護の観点から各国で利用の促進が図られています。
なぜ注目されているの?
再生可能エネルギーはおもに「非化石エネルギーのうち永続的に利用できるもの」のことを指します。つまりは「枯渇しないこと」が要件として挙げられるわけですが、ほかにも「どこにでも存在する」 「CO2を排出しない」といった化石燃料とは異なる特徴を有しています。これにより、原油枯渇問題にとどまらない多くの課題の解決に貢献していると言えます。
特に、「CO2を排出しない」という特徴は、21世紀以降の環境問題への関心の高まりに伴い大きくクローズアップされており、各国で再生可能エネルギーへの期待が高まっています。
2016年に発効した「パリ協定」では、
| ・産業革命前からの世界平均気温上昇を2℃より十分低く保ち、1.5℃程度の上昇に抑える ・そのために、今世紀後半に人為的な温室効果ガス排出量を実質ゼロにする(排出量と吸収量を均衡させること) |
の2点が世界の目標として定められており、CO2排出量をゼロに抑えられる再生可能エネルギーはその切り札として世界から注目を集めています。
これを受けて海外では石炭火力発電所の廃止に多くの国が取り組んでいるほか、再生可能エネルギー比率を引き上げる目標設定も多く見られます。EUでは加盟国全体での電源比率における再生可能エネルギー比率を2030年までに42.5%(法的拘束力のない努力目標は45%)にすることを合意しました。
国内においても2020年に「2050年までに温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、排出量を実質ゼロにする」という目標が掲げられ、再生可能エネルギー活用の動きがより一層加速しています。2021年9月に取りまとめられた「第6次エネルギー基本計画」では、2030年までに温室効果ガスを2013年度から46%削減し、そのために再生可能エネルギーの電源比率を36〜38%まで引き上げることが明記されました。(2020年の電源構成における再生可能エネルギー比率は18%)
このように現在では、世界でも日本でも再生可能エネルギーの普及は広がってきています。
資源を持たない日本にとっても重要

再生可能エネルギーの「どこにでも存在する」という特徴は、資源の多くを輸入に頼る日本にとって大きな意味を持ちます。
日本のエネルギー自給率は2019年において12.1%であり、これはOECD(経済協力開発機構)加盟国36カ国中35位と先進国の中でも非常に低い水準となっています。また、資源エネルギー庁が作成するエネルギー白書によれば、電源構成におけるLNG、石油などの化石燃料の割合は約76%(2019年)に上り、発電の多くを化石燃料に頼っている状況です。
しかし、資源の多くを海外に頼る状況では、市場の混乱や地政学的な要因の影響を強く受けやすく、エネルギー安全保障上大きな懸念があります。また、日本は化石燃料の輸入に毎年10兆円〜20兆円の支出をしており、言い換えればそれだけの資金が海外に流出していると言えます。この資金を一部でも国内投資に回すことができれば、国内の経済循環に繋がりるため、再生可能エネルギーによる発電の増加は経済合理性も高いと言えるでしょう。
また、災害が多く居住地も全国に点在している我が国において、どこでも発電できる再生可能エネルギーは電力の安定供給の側面でも有用です。2011年の東日本大震災にも代表されるように、日本の発電所は常に災害に合うリスクに晒されています。一度大規模な発電所が停止すると広範囲に渡って電力がストップし、多くの住民に影響を及ぼします。再生可能エネルギーは立地を選ばずに設置できるため、集中型エネルギーの供給が途絶えた場合でも最低限の電力を賄える非常用エネルギーとしても再生可能エネルギーへかかる期待は大きいです。
ここまで見てきたように、「環境問題の観点」「エネルギー安全保障の観点」「災害対策」などの観点から再生可能エネルギーの活用の重要性は非常に高いと言えます。以上の理由もあり、再生可能エネルギーに集まる期待は日に日に大きくなっているのです。
自然エネルギー、次世代エネルギーなどとの違いは?

環境や資源に関する関心が世界的に高まる中で、国内でも関連するエネルギーに対する様々な区分が誕生してきました。しかし、それぞれの区分は重複する部分が多いため違いが分かりづらいことも多くあります。ここでは、再生可能エネルギーとよく混同される「自然エネルギー」「新エネルギー」「次世代エネルギー」の3区分の違いを見ていこうと思います。
自然エネルギー
「自然エネルギー」は字が表す通り自然現象がもととなって得られるエネルギーのことを指します。自然から得られるエネルギーは再生が可能なため、再生可能エネルギーの一部とされます。例えば、太陽光、風力などは自然エネルギーに含まれますが、バイオマスなどは自然現象そのものからエネルギーを得ているわけではないので自然エネルギーには含まれないとされます。
一方、自然エネルギーは自然から直接得られるエネルギー(=一次エネルギー)と定義されることもあり、その場合には天然ガスなどの枯渇性資源が含まれることがあり、注意が必要です。
新エネルギー
「新エネルギー」は「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(新エネルギー法)」の施行令の中に定められたバイオマス、太陽熱、太陽光など10種のエネルギーのことを指します。現状、新エネルギーはすべて再生可能エネルギーとなっています。
新エネルギー法は非化石エネルギーのうち、経済的な理由(高コストなど)から十分に普及していないエネルギーの普及促進を図る法律です。そのため、新エネルギーは国が特に力を入れて普及を推進しているエネルギーと言えるでしょう。
次世代エネルギー
「次世代エネルギー」とはいま現在世界で主に使われている化石燃料の代替となりうる各種エネルギーのことです。再生可能エネルギーを含む幅広いエネルギーの総称とされていることが多いです。再生可能エネルギーは「どこにでも存在し、再生可能であること」が要件となることが多いため2次エネルギーなどは含まれませんが、次世代エネルギーには含まれます。再生可能エネルギーではない次世代エネルギーとしては、近年魅力的なエネルギーとして注目を集める「水素」などが挙げられます。
次世代エネルギーの多くは非枯渇性とCO2排出量の少なさが特徴であり、資源問題と環境問題の双方を解決するキーとして世界中で研究や開発が進められています。
| ポイント | 含まれるもの | |
| 再生可能エネルギー | 持続的に再生可能 | 自然エネルギー、バイオマスなど |
| 自然エネルギー | 自然現象から得られる | 新エネルギー、大規模水力、(天然ガス)など |
| 新エネルギー | 政府が利用を促進 | 太陽熱、地熱、太陽光、風力など10種 |
| 次世代エネルギー | 石油資源に代わるエネルギー | 再生可能エネルギー、水素、燃料アンモニアなど |
再生可能エネルギーを利用した発電の種類

再生可能エネルギーの利用方法には電気に変換する「発電利用」の他にも、発熱現象や地熱を直接使う「熱利用」、風力や水力を用いた「動力利用」など様々な形態があります。ここでは発電利用のうち、実用化されている代表的なものをピックアップしてご紹介します。
太陽光発電
太陽の光エネルギーを太陽電池を用いて直接電気に変えるシステムです。設置の容易さから一般家庭にも多く普及しています。メンテナンスが容易で、非常用電源としての活用もできますが、天候によって発電量が左右されるため、電力の安定供給に課題があります。
風力発電
風車の回転運動を発電機に伝えて電気を作る発電システムです。大規模に開発した場合にはコストを抑えることができ、場合によっては発電コストが低いとされる火力発電や大規模水力発電と同等のコストでの発電も可能となります。一方で、広い土地が必要になるほか、騒音問題や風量、地質の関係で適地も限られます。
水力発電
河川などの高低差を利用して水を落下させ、その際のエネルギーで水車を回して発電する方式です。安定して長時間の運転が可能で信頼性が高いことが特徴です。また、中小規模型は設置可能場所が多く大規模発電に依存しない分散型電源として期待されています。一方で、事前調査には時間がかかるほか、中小規模型については相対的に発電コストが高くなるデメリットもあります。
地熱発電
地下に蓄えられたエネルギーを蒸気や熱水の状態で取り出し、タービンを回して発電する方式です。出力が安定しており、大規模開発が可能なほか、昼夜を問わず発電できますが、長期間の開発期間が必要で費用も高額になることがデメリットとしてあげられます。
バイオマス発電
動植物などの生物資源をエネルギーにして発電する方式です。木質バイオマス、農作物残さ、食品廃棄物などが資源として利用されます。廃棄物の削減につながるほか、天候に左右されずに発電できますが、原料の安定供給や収集、運搬にコストを必要とします。
次世代エネルギーの種類

化石燃料時代の次の時代を担う新しいエネルギーには再生可能エネルギー以外にもさまざまな種類が存在します。ここでは、次世代エネルギーのうち、代表的なものである「水素エネルギー」「燃料アンモニア」と、次世代のCO2排出量削減に大きく貢献するかもしれない技術である「CCS技術・CCUS技術」についてご紹介します。
水素エネルギー
水素は燃焼の際にCO2を排出しないほか、酸素と反応させて発電することもできるため「水素発電所」「水素熱発電所」で発電に使われています。酸素と反応させる水素発電はエネルギー変換を経ずに直接発電できるため発電効率がいいことでも知られています。それ以外にも燃料電池車やエネファームなど生活に身近な場面でも新しいエネルギーとして活用されています。
燃料アンモニア
水素と大気中の窒素を反応させることでできるアンモニアは液化水素やMCHといった他の水素運技術搬と比べて、安価で安定的な運搬が可能であるため、水素の輸送媒体として注目を集めています。また、アンモニア自体も燃焼することができるため、石炭と混ぜて火力発電を行いCO2排出量を減らす研究が進んでいます。いずれはアンモニアのみで発電する「アンモニア火力発電」の確立も目指されています。
CCS・CCUS
CCSとCCUSはともに発電所や化学工場から排出されたCO2の排出量を抑えることが可能となる技術です。CCS技術は「二酸化炭素回収・貯留」技術と呼ばれ、工場等から排出されるCO2を地下深くに貯留する技術となります。
CCUS技術はCO2を貯留するだけでなく利用もするための技術です。米国においては油田へCO2を注入し、その圧力で原油を押し出す技術が実現されています。国内においても化学原料の生産に使うことなどが検討されています。
まとめ
再生可能エネルギーは、世界の次世代を担うエネルギー源として今後ますます注目を集めていきます。また、環境問題や資源枯渇問題に対して、様々な再生可能エネルギーを組み合わせながら有効に対処していくことがより一層求められていくことでしょう。いままさに成長著しい再生可能エネルギー分野に興味を持つことで、環境問題や資源問題といった様々な地球規模の課題への理解もより深めることができるのではないでしょうか。
コラム:FIT制度とFIP制度
再生可能エネルギーの導入拡大に向けて、国内では税制優遇や補助金・助成金の交付といった様々な支援策が国・地方自治体問わず整備されてきました。ここではその中でも再生可能エネルギーに関わる方であれば一度は耳にすることのあるFIT制度とFIP制度について解説していきます。
FIT制度(固定価格買取制度)
政府は再生可能エネルギーの導入拡大を図るために「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「FIT法」)」を制定しました。これに伴い2012年7月から導入されたのがFIT制度です。
FIT制度は送配電事業者に対し、個人や事業者が再生可能エネルギーによって発電した電気を一定期間(10年間または20年間)、一定価格で買い取ることを義務付ける制度です。FIT制度における買取価格は、制度を使用しない際の買取価格より高く設定されています。
当制度を利用することにより、発電設備設置者は建設・設置コストの見通しが立ちやすくなり、普及促進につなげることができます。
現在、発電の種類と規模によっては後述のFIP制度のみが対象となっていますが、一般に家庭で使用される発電出力50kW未満の太陽光発電などはFIT制度の対象となっています。
FIP制度
FIT制度は再生可能エネルギーの導入拡大に大きく貢献しましたが、同時に様々な課題が出てきました。
その1つが「再エネ賦課金」の問題です。FIT制度の買い取りコストの一部は電気料金に上乗せして徴収されている再エネ賦課金によって賄われていますが、その負担は再生可能エネルギーの拡大に応じるように大きくなって来ています。
また、発電した電力を固定価格で買い取ってもらえるFIT制度下では、電力事業者は需給バランスや価格競争のリスクにさらされずに供給を行えていました。しかし、再生可能エネルギーを主力電源とするに当たっては需要を踏まえた発電システムとなる必要性も論じられてきていました。
そこで、2022年4月から導入されたのがFIP制度です。FIP制度は発電事業者が再生可能エネルギーで発電した電力を、卸電力市場で自由に売電させ、その売電収入に「プレミアム」と呼ばれる補助金を上乗せする制度です。
事業者収入=市場価格+プレミアム
プレミアムは「基準価格」と呼ばれる補助後の期待収入と「参照価格」と呼ばれる市場取引での期待収入との差額で決まります。
基準価格に関しては再エネ電気の供給に必要な費用をベースに予め設定されます。参照価格は市場価格に連動し、1ヶ月単位で変動します。また、参照価格にはFIP制度対象の電力事業者に求められる「バランシング(発電量の見込みである「計画値」と実際の発電量である「実績値」を一致させること。差が出た場合には差を埋めるための費用がかかる)」にかかるコストも考慮されています。
以上から、電力事業者は市場価格の高いタイミングで電力を売却することが利益追求に繋がります。電力事業者は市場価格変動に伴い、電力需給を意識した発電が求められるのです。
なお、同制度の対象は発電量が50kW以上のすべての発電事業者で、発電種別と規模によってはFIP制度のみが認められます。FIT制度が認められる発電種別においてはFIT制度かFIP制度の選択が必要になります。さらに、すでにFIT認定を受けている電源についても対象となる発電量があればFIP制度に移行することもできます。
申請
FIT制度・FIP制度を利用するためには経済産業省から事業計画の認定が必要になります。家庭用など低出力太陽光発電(50kW未満)の場合でもFIT制度を利用するためには「事業」としての申請が必要となりますが、代行業者による委任申請も認められています。申請が認められれば、固定価格での買い取りが電力会社に義務付けられているFIT法に基づきFIT制度が適用されます。
一例として、太陽光発電の事業計画認定の大まかな流れを記載します。
太陽光発電の場合
1.事業計画策定ガイドラインを踏まえて事業計画を策定
2.立地・設備などについて検討(家庭用の場合見積もり取得)
3.電力会社に接続契約・特定契約(・発電量調整供給契約/事業用の場合)申し込み。接続契約締結
4.経産省に事業計画認定の申請・認定
5.特定契約締結
6.着工と完成
7.試運転(使用前自己確認/使用前自己検査)
8.電力供給の開始
9.定期報告
詳細については資源エネルギー庁の特設サイトに記載がありますので、そちらをご覧ください。
・資源エネルギー庁 「なっとく!再生可能エネルギー」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/index.html
再生可能エネルギーの転職・求人情報
- 国内大手建設会社での新エネルギーエンジニアリング/年収:~1000万円/東京都
- 上場不動産会社における再生可能エネルギー施設の開発用地取得営業/年収:~800万円/東京都
- 上場不動産会社における再生可能エネルギー施設のアセットマネジメント(運用管理)/年収:~800万円/東京都
- 再生可能エネルギー事業会社でのEPC営業(シニアメンバー)【契約社員】/年収:~1000万円/東京都
- 再生可能エネルギー開発会社での経営企画(データ分析)/年収:~800万円/東京都
- 【フルフレックス(福岡/東京)】再生可能エネルギー事業会社でのテクニカルアセットマネージャースペシャリスト【契約社員】/年収:800万円~1200万円/福岡県
- 再生可能エネルギー事業会社でのクラウドインフラエンジニア/年収:~1000万円/東京都
- 大手金融機関系リスクマネジメント会社での蓄電池リスクアドバイザー/年収:~1200万円/東京都
- 再生可能エネルギー会社での再生可能エネルギー発電所開発プロジェクトマネージャー/年収:~1000万円/東京都
- 【東京/仙台】再生可能エネルギー事業会社での太陽光発電所のアフターセールス業務(東北担当)/年収:~800万円/宮城県
- 【愛知(犬山)】再生可能エネルギー事業会社での太陽光発電所 保守管理業務【契約社員】/年収:~800万円/愛知県
- 大手PEファンドでの再生エネルギー・サステナビリティ投資業務<VPクラス>/年収:~800万円/東京都
- 【東京/福岡】再生可能エネルギー事業会社でのEV事業開発リーダー【契約社員】/年収:800万円~1000万円/東京都
- 【北海道/青森/秋田】大手商社系再生可能エネルギー開発会社におけるETS|運転・保守担当/年収:~800万円/お問い合わせください。
- 大手商社系再生可能エネルギー開発会社における土建エンジニア(陸上/洋上)/年収:~1200万円/東京都
- 株式会社三菱UFJ銀行/グローバルバンクでの再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理/年収:~1600万円/東京都
- 大手銀行での再生可能エネルギー・電力関連の新規事業企画開発/年収:~1400万円/東京都
- 再生可能エネルギー事業会社でのコマーシャル アセットマネージャー【契約社員】/年収:~1000万円/東京都
- 【北海道・秋田】大手商社系再生可能エネルギー開発会社における風力発電所 運転・保守業務担当/年収:~1000万円/お問い合わせください。
- 再生可能エネルギー事業会社での連結会計担当/年収:~800万円/東京都
- 【東京/大阪勤務】経営コンサルティング会社でのコンサルタント(再生可能エネルギー)/年収:~800万円/東京都
- 大手証券系投資会社 再生可能エネルギー投資担当/年収:~1600万円/東京都
- 大手金融機関系リスクマネジメント会社でのリスクコンサルタント【再生可能エネルギー分野】/年収:~1000万円/東京都
- 大手証券系投資会社での再生可能エネルギー アセットマネジメント/年収:~1600万円/東京都
- 再生可能エネルギー開発会社でのコーポレートPPA事業開発(若手)/年収:~800万円/東京都







